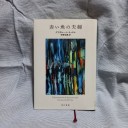「うっせぇわ」は誰の歌か。
2021年12月20日 備忘録 コメント (4)日本人の平均年齢47歳とか10代がマイノリティであるとか、考えたこともなかった。
団塊世代、団塊ジュニア、そしてその子ども世代、見えてる景色、空気まったく違うの当たり前か。
<「うっせぇわ」を聞いた30代以上が犯している、致命的な「勘違い」
わかった気でいる年長者に言いたいこと>
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/80819?imp=0
・・・
2019年の日本の人口ピラミッド。
上の世代が重い。
ポコッとへこんでる53歳、1966年生まれ。なぜこの年出生数が少なかったんだろう?
ググった。びっくり!
丙午(ひのえうま)だからだって!
そんな迷信で人口がこんな目に見えるほど変わるなんて。。
次の丙午は2026年。
大丈夫だろうか、日本。。。
・・・
<追記>
日本の平均年齢が47歳と聞いても、へぇ、、で意味が解らなかったんだけど。
世界人口統計を見てみたら世界最高齢だった。
平均寿命が延びた、長生きの国、めでたい的な切り取りでしか考えてなかったけど。平均年齢47歳は断トツ単独1位。次がイタリアの45歳、ドイツ、ポルトガル、ギリシャが44歳。ヨーロッパは中年国家多いけど。
日本の人口ピラミッド見ると、ここ40年くらい丙午の1966年の出生数すら超えてない。ピラミッドというより壺。
ってことを今更認識したからどうだって話だけど。
私自身、子ども人口増やすことに貢献しなかったし。
まあ、なんというか、ほんとにもういろいろ諦念に包まれるなぁってだけの話。
あすこのパウンドケーキ
2021年12月16日 日常父が入院していた病院の向かいに小さなパン屋があって。
「あすこのパウンドケーキが美味しいんだよ」と何度となく父が言っていた。
絶飲食が解かれたら珈琲とそのケーキを食べるのを楽しみにしてた。
食べられなかったけど。
近くに行ったのでお店に寄ってパウンドケーキを買った。
たまにしか行かないけど、行ってご高齢の主人夫婦が揃っているのを見るとホッとする。ここでもPayPayが使えるようになってた。そういえば建て替えられてお店が新しくなってから何年経つかな。父が知ってるのはモルタル二階建ての昭和なパン屋だった。
ケーキを買って自転車を走らせていると、懐かしくて泣きそうになる。
10年経ってもこんな気持になる。お父さんはいないけどいる。
ついでのように思う。
階下のひとはこんな風に思い出されることはないんだなと。すこし可哀想だなって思ったけど、それは私もそうだ。
この世界から消えて10年経って、思ってくれるひと、いないな。
別に悲しくもないけど。ふと思っただけ。
どっから流れてきたんだろ?
ギターが鳴ってピアノが弾けて。
あ、このイントロ好きかも。
……everything everything
女声が歌いだす。
……果てなき世界の 形なき道筋
男声が入ってくる。
わっ、この声好きかも!
……This way
シャウト!
えっ?! あーー!チバじゃん!!
なにこれーー??
BUGY CRAXONEというバンドのアルバムにゲストヴォーカルで参加してた。
2002年。まだミッシェルの頃。女声に合わせるチバの声って珍しいかも?
チバの曲と歌い方が少し違ってて歌いだしではわからなかったけど、好きな声ってやっぱりどう聴いても好きだ(表現オカシイ、けどヨシ)
こういう曲調というかサウンド、なんていうんだ?ダブ?違うか。よくわからないけど嫌いじゃない。
で、音源欲しくてAmazonでポチる。
・・・
ふぅ~ん。しかし “声” っていうのは、替えが効かないというか。
まあ、だからヴォーカルがバンドのフロントになるわけなんだろうけど。
MICHELLEやTheBirthdayのコピーバンドが結構あるみたいで。
ちらっと見てみたけど。ア リ エ ナ イ としか(汗)
ナニユエ、チバノカワリニウタオウトオモウンダロウ、と。
うん、いや、いいんだけど。愛の形もリスペクトの表現もそれぞれなんだから。
でもどんなに頑張ってバンド組んでも、チバや清志郎の “声” はコピーできないよなぁと思う。彼らの声は Copy Control されてると思う。
秘密の裏庭。
天気が下り坂だというので、昨日陽射しの暖かな午後に。
紅葉の終わりと結実の盛り。
ああ、ここは晩秋から冬が良いなぁ。
春・夏ももちろん美しいけど、虫が多くてゆっくりできない。
虫、嫌いじゃないけど、のべつまくなしに襲ってくる蚊はうるさくてのんびり座ってもいられない。初夏の毛虫の季節はうっかりベンチに腰も下ろせないし、樹の上から降ってくるし。
ここにくると、ひとりごとが多くなる。
踏んで歩く草地の柔らかさに、わぁ~ふかふかだね~。
カエデの赤い絨毯に、わぁ~すご~い。
きれいだねぇ~美しいねぇ~、ああ~なんて気持いいのぉ~。
大きな樹や枯れ草やもぐら塚や、赤や青や黄色い実に、愛してるよ~と伝えたくなる。声にだして。
犬や猫に話しかけちゃうひと以上に怪しいかもね。
でもいいの、誰もいないんだから。
・・・
強く風が吹いて、スギかなヒバかな、大きな針葉樹が鳴る。
広葉樹の軽い葉擦れの音ではなくて、樹全体が揺れて軋んで立てる重たい音。
ギーゴゴゴゴ。ざわざわざわ。
そして良い匂いがする。アロマオイルでシダーウッドなんて名前がついてる匂い。それの最高にフレッシュな。
ここでは黙って耳を澄まし深く呼吸する。
竹林が鳴る。
カラカラカラカラ、、、コーンコーン。さわさわさわさわ、、コーン。
・・・
今日は雨が降っている。
雨の音も好きだし雪の日の静寂の音も好きだけど、自然の音の中で樹木の鳴る音が一番好きかもしれない。
・・・
風が大きく樹を揺らすのを見ながら樹の鳴る音を追って歩いていて気が付いたんだけど。
ひらけた草地の上空を軍用機が何度もなんども横切って飛んだ。
西に向かって、福生の方角かな。旅客機と違って低い位置を飛ぶからひらけた野外でも、聴いている風と樹の音とはあきらかに違う音が混じってきて耳に障る。
日本の制空権はアメリカのもの、というのを思い出してしまう。
帰り道
帰り道に君は言うだろう 愛と憎しみはどう違うのって
帰り道に僕は言うだろう どこも違わないどっちも真実だって
細かな雨をワイパーが拭き取って 散らばったネオンがぬれてる
しびれた左腕を気にしながら どうしてオルガがさっき泣いてたのか
首を右に傾けて考えている
3コードで魂を失くしたジャンキー 3コードで宇宙に行くって言って
今じゃ電磁波にヨダレたらしてる
帰り道に君は言うだろう 神様ってどこにいるのって
帰り道に僕は言うだろう ジミヘンはモジャモジャの中さって
昨日の夜ゴミ箱が燃えてた なんだかすごくきれいで
僕はずっと見とれてたよ
警報器が鳴って大雨が降った 嫌な音階を水が消してた
君は耳に無線をつけて 画家の伝記映画に夢中だ
僕はびしょ濡れの服をはたきながら
丸くない星ってあるのかなって考えてた
帰り道に君は言うだろう 愛と憎しみはどう違うのって
帰り道に僕は言うだろう どこも違わないどっちも真実だって
僕は未だに3コードに恋をしていて ブルーズにまみれてる
ハッピーなのは君と寝そべって 君の横顔を見ている時だけで
ぶっとんでるのは 弦が2本しかないギターを弾いている時だけさ "Yeah!"
帰り道に君は言うだろう 神様ってどこにいるのって
帰り道に僕は言うだろう ジミヘンはモジャモジャの中さって
「酔いどれ詩人になる前に」
明日の天気は――人新生
2021年12月7日 備忘録 コメント (4)人新生という語を目にしたのはつい最近。
『人新世の「資本論」』という本のレビューをTweetで見て。
地質年代を上書きするレベルで人の活動が地球を変えてしまったんだと、その言葉のインパクトに驚く。
オゾン層の破壊とか温暖化とか警鐘鳴らされてたのはいつからだっけ?
……というような無責任な問題意識の希薄さの帰結。
「人新生」wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%96%B0%E4%B8%96
「北海道の米が美味しくなったのは温暖化のおかげ」とか言ってる老人を嗤う私自身も、この経済的繁栄の時代を生きて恩恵(負債に思いをはせぬまま)を受けてきたから、責任は同等かもしれない。
庭やベランダで植物を育てている人には窒素、リン酸、カリって、肥料として普通に聞く要素だと思うけど、このリン酸がもう何年かしたら入手が困難になってくるらしい。
日本の火山灰の多い土壌はこのリン酸が乏しいらしく、日本の農地は膨大なリン酸を投入して成り立ってるらしい。なぜリン酸を大量に必要とするのかというと、もとが外国産の野菜なのでリン酸がないと十分に育たないから。だから、リン酸が手に入らなくなったら日本の農業は立ち行かないと。
そこから、その土地の土壌にあった作物、在来種を作ることを考えようとなるんだけど、その在来種は自家採取することも禁じられて(禁じられようとして?)いて……と。
日本の土壌にリン酸が乏しいとか、日本の土がどんな土なのか考えたこともなかった。世界規模でリン酸が不足するかもとか聞いても、え?まじ?地球のどっかに栄養素含んだ土なんていっくらでもあるんじゃないの?なんてビックリする。
どんな土も、無尽蔵ってどっかでうすらぼんやり思ってた。まったくウスラボンヤリだ。地球の土壌って薄い紙一枚くらいの厚みしかなくて、有用な土壌、鉱物は限りがある。
地球の資源には限りがあるというのは、ずいぶん前から聞くフレーズだったけど、「うんそうだよね、地球って閉じた惑星なんだから確かに有限だよね」くらいのイメージで自分が生きてるうちにその限界が来る可能性とかリアリティをもって考えたことなかった。
Wikにある9つの限界点、どれも何となく知ってたよね。
引き返し不能点(ティッピング・ポイント)をじわじわと超えつつある。
何年か前に野口勲の「タネが危ない」を読んだ頃には、モンサントの陰謀くらいの話で浅い理解しかなかったけど、その背景でもっといろんなことが進行してて。
いまや人類含む生物の生存を守ってきた地球システムが壊れようとしてる。
……と自分で書いてて、なにこの壮大な陰謀論的近未来SFは?って笑いそうになるけど、「明日の天気は晴れかな、雨かな」くらいの想像力ではもう追いつかないよね。
Covido-19の蔓延する世界だっていきなり始まったんだから、9つの限界点超えた世界が明日いきなり始まらないとは言えない。
私のベランダの軒下で、大きくなりすぎて自重で崩壊したアシナガバチの巣みたいなカタストロフィがいきなり来るかもしれないね。
いや、来るんだろう。来るんだよ。
……そう言い聞かせつつ、どうしたらいいのかわからないのでどっかで諦めてる。ほんとにグレタさん世代にごめんなさいとしか。(あ~軽いなぁ~)
5億年くらい先の未来にどこかの星で生まれ変わって、地球の惑星調査に来て、人新生を掘り起こしてみたい。
そのころ地球は何色をしているだろう。
『人新世の「資本論」』という本のレビューをTweetで見て。
地質年代を上書きするレベルで人の活動が地球を変えてしまったんだと、その言葉のインパクトに驚く。
オゾン層の破壊とか温暖化とか警鐘鳴らされてたのはいつからだっけ?
……というような無責任な問題意識の希薄さの帰結。
「人新生」wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%96%B0%E4%B8%96
グレート・アクセラレーション
社会経済システムと地球システムの12の指標が、20世紀後半から急速に上昇傾向にあるという仮説を指す。開始時期については1945年、1950年代など諸説がある。この仮説は2004年から使われている。
社会経済システムの指標:人口、国内総生産(実質GDP)、対外直接投資(FDI)、都市人口、一次エネルギーの使用、化学肥料の使用、巨大ダム、水利用、製紙、交通、遠隔通信、海外旅行となる。
地球システムの指標:二酸化炭素、亜酸化窒素、メタン、成層圏オゾン、地球の表面温度、海洋酸性化、海洋における漁獲量、エビ養殖、海洋の富栄養化や無酸素化につながる沿岸窒素の増加、熱帯雨林と森林地域の喪失、土地利用の増大、陸上の生物種の推定絶滅率となる。
これらの指標は20世紀後半から急速に上昇傾向にあり、地球環境の負の方向への変化を示している。グレート・アクセラレーションの考え方が普及するまでは、地球環境問題は温暖化などの個別の指標の分析にとどまっていた。
「北海道の米が美味しくなったのは温暖化のおかげ」とか言ってる老人を嗤う私自身も、この経済的繁栄の時代を生きて恩恵(負債に思いをはせぬまま)を受けてきたから、責任は同等かもしれない。
プラネタリー・バウンダリー
人類がもたらした変化が、地球の限界を超えつつあるという警告を含む仮説を指す。地球をシステムとして考えると、恒常性を維持するフィードバックが働いている。しかし、引き返し不能点(ティッピング・ポイント)を超えると、システムは予想がつかない振る舞いをする。この仮説は2009年に発表された。当初の提唱者は、地球システムを研究するスウェーデンの環境学者ヨハン・ロックストロームと化学者のウィル・ステフェンをはじめとする約20名の研究者だった。
仮説では9つの限界点を指標にしており、機能によって3種類に分けられる。
1.地球的な閾値が明確に定義されたもの:気候変動、成層圏オゾン層の破壊、海洋酸性化。
2.緩やかに変化する地球環境にかかる変数にもとづくもの:土地利用の変化、淡水利用、生物多様性の喪失、窒素とリンの循環。これらは緩やかな限界値とも呼ばれる。
3.人類が作り出した脅威:大気エアロゾルの環境に負荷を与える化学物質、重金属や有機化学物質による生物圏の汚染。
この中で、気候変動、生物多様性の損失、生物地球化学的循環は2009年時点で限界を超えたともいわれている。
庭やベランダで植物を育てている人には窒素、リン酸、カリって、肥料として普通に聞く要素だと思うけど、このリン酸がもう何年かしたら入手が困難になってくるらしい。
日本の火山灰の多い土壌はこのリン酸が乏しいらしく、日本の農地は膨大なリン酸を投入して成り立ってるらしい。なぜリン酸を大量に必要とするのかというと、もとが外国産の野菜なのでリン酸がないと十分に育たないから。だから、リン酸が手に入らなくなったら日本の農業は立ち行かないと。
そこから、その土地の土壌にあった作物、在来種を作ることを考えようとなるんだけど、その在来種は自家採取することも禁じられて(禁じられようとして?)いて……と。
日本の土壌にリン酸が乏しいとか、日本の土がどんな土なのか考えたこともなかった。世界規模でリン酸が不足するかもとか聞いても、え?まじ?地球のどっかに栄養素含んだ土なんていっくらでもあるんじゃないの?なんてビックリする。
どんな土も、無尽蔵ってどっかでうすらぼんやり思ってた。まったくウスラボンヤリだ。地球の土壌って薄い紙一枚くらいの厚みしかなくて、有用な土壌、鉱物は限りがある。
地球の資源には限りがあるというのは、ずいぶん前から聞くフレーズだったけど、「うんそうだよね、地球って閉じた惑星なんだから確かに有限だよね」くらいのイメージで自分が生きてるうちにその限界が来る可能性とかリアリティをもって考えたことなかった。
Wikにある9つの限界点、どれも何となく知ってたよね。
引き返し不能点(ティッピング・ポイント)をじわじわと超えつつある。
何年か前に野口勲の「タネが危ない」を読んだ頃には、モンサントの陰謀くらいの話で浅い理解しかなかったけど、その背景でもっといろんなことが進行してて。
いまや人類含む生物の生存を守ってきた地球システムが壊れようとしてる。
……と自分で書いてて、なにこの壮大な陰謀論的近未来SFは?って笑いそうになるけど、「明日の天気は晴れかな、雨かな」くらいの想像力ではもう追いつかないよね。
Covido-19の蔓延する世界だっていきなり始まったんだから、9つの限界点超えた世界が明日いきなり始まらないとは言えない。
私のベランダの軒下で、大きくなりすぎて自重で崩壊したアシナガバチの巣みたいなカタストロフィがいきなり来るかもしれないね。
いや、来るんだろう。来るんだよ。
……そう言い聞かせつつ、どうしたらいいのかわからないのでどっかで諦めてる。ほんとにグレタさん世代にごめんなさいとしか。(あ~軽いなぁ~)
5億年くらい先の未来にどこかの星で生まれ変わって、地球の惑星調査に来て、人新生を掘り起こしてみたい。
そのころ地球は何色をしているだろう。
私は絵本では育たなかった。
マンガで字を覚えて、そのまま物語を読み始めたからな。
おとなになってから手にとることが増えた。
でも私は、絵本の読み方がわかってない。気がする。
図書館で借りて眺めたあとでやっぱり手元に置いておきたくなる。
手元に置いて手懐けたい、みたいな。
どう扱ったらいいかいまいちわかんないんだけど、仔猫拾っちゃったみたいな感じかも?
今年の冬至は22日。まだ3週間もある。
冬は好きなのに12月が苦手で。
弱々しく衰えてゆく太陽の光を見てると寂しくなって家出したくなる。
竹箒を買おう。
穂先が短くなってしまって、庭の落ち葉を軽く掬えなくなってきた。
もう十年以上使ってるから仕方ない。
すこしずつ、お父さんが手にした道具じゃなくなってゆく。
大雨の夜、雨上がりの朝。
2021年12月1日 日常夜中に目が覚めたのは、屋根を叩く雨の音が尋常じゃなかったせいか、頭が痛かったせいか。低気圧のせい。
頭が痛くて目が覚めるなんて、そんなことあまり記憶にないけど。
出勤する頃には雨も上がっていたので助かった。
大雨の後の空がきれいで、空気もきれいで、濡れた庭の落ち葉もきれいで。
ヒメコブシの葉がだいぶ落ちてしまった。
駅に向かう途中に掃き寄せられた、まだ青いイチョウと赤く色づいた桜。
やっぱり「洋菓子店」でしょ。
パティスリーなんちゃらではなくて、洋菓子店のケーキが好き。
最初の職場が新宿三丁目で、伊勢丹の地下には宝石のようなチョコレートやケーキが並んでたので浮かれてけっこう食べたけど、割とすぐに飽きた。
薄いタルト生地の上の栗のムースに生クリームが塗ってあって、その上に栗のクリームがこれでもかと雪崩起こしてるモンブランとか、これはワタシ的にはケーキじゃない。生クリーム盛り?
私は小麦粉をしっかり焼き上げたスポンジを味わうケーキが好き。
ショートケーキとかロールケーキとかね。モンブランもカップケーキのなかにスポンジが詰まってるのが好き。うん、オールド・ファッションなんです。
で、日本のケーキを絵に描いたような近江屋洋菓子店のケーキが好き。
先日前を通りかかったらパウンドケーキがどどんと積みあがってた。
小麦粉焼き上げたケーキの代表格パウンドケーキが実は大好きなんだけど、近江屋ではイートインしかしてなかったので買ったことなくて。
見たら無花果のパウンドで、焦げ茶色が美味しそうで。
カウンターで受け取ったときの持ち重りのする掌の感触に期待が膨らみ、そして期待を裏切らない美味しさだった。
焼きあがった生地の「しっとりと、軽さ」のバランス、香り、後味、ドライ無花果の膨らみ具合、控えめなクルミの混ざり具合、てっぺんの焦げ具合まで、大好きだー!
これはまた買わなくてはと思って、昨日寄ったらパウンドはもう終わっていて、コロナでイートインはできないしどうしようかなぁと悩んでたら、ショウウインドウの端っこにバームクーヘンがあるではないか。
ここのバームクーヘンなら間違いはないはず、と購入。間違いはなかった。
というか、マイベスト・オブ・バームクーヘンかも。
バームクーヘンは、スーパーやパン屋や、なんならMUJIとかでも気軽に買って食べるけど、本場のドイツの味ってちゃんと知らない。結婚式の引き出物の定番ユーハイムってそんなだったかな?印象薄れてるけど。
私の好みはどっしりしてるけど重くない、しっとりしてるけど乾いている、小麦とバターの味がする、そんなタイプ。
近江屋のバームクーヘン、そんなタイプ。
HP見たら、ちゃんと職人が生地を手がけして焼いてるらしい。
オールド・ファッション、万歳♡
やっぱり洋菓子店、素敵。
朝陽を浴びて濃いオレンジ色が美味しそうだったので、今日は蜜柑狩り。
20キロ入るフェルトポットにたっぷり2杯分の収穫。
一昨年の冬に、伸びすぎた枝をかなり伐り詰めてコンパクトに剪定したので去年はあまり実がつかなかった。そのぶん今年はよく実った。
摘果とか混みあった枝を伐るとかやらないので、実の大きさはまばらだし熟し具合もまちまちだけど、ほったらかしのおうち果樹がこれだけ実をつけてくれるんだから嬉しい。糖度はさほど高くないけれど、果汁はたっぷりで酸味が少ないので十分に美味しい。
この蜜柑狩り、いつまでやれるかなぁ。
180㎝の脚立にあがってぎりぎり。樹冠の中心あたりだと手が届きにくいので足元が不安な時あるし。いっそブロック塀に立って木の枝の間に身体を入れてしまったほうが安定するんだけど、そういうお転婆も昔ほど自信満々にはやれなくなってきたし。
で、いま三点脚立を買おうかどうしようか悩んでいる。
普通の脚立は大中小あるんだけど、庭木の剪定するのには高さが足りないのと、四点支持なので砂利やでこぼこのある庭に置くと安定しなくて。
240あればいいかな? 300あってもいいかな?
大は小を兼ねる?でも庭石や樹のある狭い場所で取り回し辛いかな?
とりあえずホームセンターで現物見てこよう。
A Case of You
2021年11月26日 音楽James Blake - A Case Of You (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=IG2E3qyFqsw
(Rendez-vous 30:21)
Joni Mitchell-A Case of You
https://www.youtube.com/watch?v=0YuaZcylk_o
Just before our love got lost you said,
"I am as constant as a northern star."
And I said, "Constantly in the darkness,
Where’s that at?
If you want me I’ll be in the bar."
On the back of a cartoon coaster
In the blue TV screen light
I drew a map of Canada
Oh, Canada
With your face sketched on it twice.
Oh, I am a lonely painter
I live in a box of paints.
I’m frightened by the devil
And I’m drawn to those ones that ain’t afraid.
I remember that time you told me
You said, "Love is toching souls."
Surely you touched mine.
’Cause part of you pours out of me
In these lines from time to time.
I met a woman
She had a mouth like yours
She knew your life
She knew your devils and your deeds.
And she said, "Go to him, stay with him if you can
but be prepared to bleed."
Oh, but you are in my blood
You’re my holy wine
You’re so bitter
bitter and so sweet.
Oh, I could drink a case of you darling
still I’d be on my feet
I would still be on my feet.
Joni Mitchell 『Blue』 1971
サウンド&アート展 ― 見る音楽、聴く形
2021年11月22日 すこし遠いどこか。 コメント (2)アーツ千代田3331でやってた「サウンド&アート展」を覗いてきた。
https://muse-creative-kyo.com/caec/soundandart/
「見る音楽、聴く形」すごく好みのコンセプトだしね。
たぶん好きなインスタレーションが並んでるだろうと思って。
で、好きなインスタが並んでたけど、残念、会場が小さ過ぎたね。
音の鳴る作品が、すぐ近くに並んでいて、一度にデモやったらせっかくの音が干渉し過ぎちゃうから自由に聴くことができない。だから、音を生む作品がつまらなそうに沈黙してただけ。
ひと作品ひと部屋くらいで展示して欲しかったな。
デモンストレーションの時間が限定されてたので、ひとも集まっちゃうし、気配のざわめきもあって音が生まれてくることに耳を澄ますことができなかった。
ダクソフォンのパーツを壁に展示してあったんだけど、その音色は横に置いたヘッドホンで聴くとか。Boomwhackersは壁掛けのモニター見ながらヘッドホンで聴くとか。
ぜん、ぜん、面白くないじゃーん。
ダクソフォンなんて、個室で内橋さんをとは言わないけど音大の学生でも連れてきて奏でさせたら良かったのに。ロングパイプだって自由に振らせたらよかったのに。
クラドニ図形を描く鉄板とか、クルミを投げて鐘の音を鳴らす亀裂の入ったテーブルとか、落下する竹や金属パイプがたてる微けき音とか、楽しくて気持のよい作品もいろいろあったけど、ともかく見せ方、聴かせ方間違えてるよなぁ。
音の生まれる瞬間を聴くには、その前後に長い静寂が必要じゃないの?
音と静寂は対だよね。
Humming Bird
2021年11月22日 チバ コメント (2)「人生は一度きりなのだし、コロナ禍を随分色々我慢して来たし。
ワタクシ箍が外れているのかも知れませんが、買いましたーー!」
ありすさんの日記読んでうふふふふ~♪
ええ、ええ、箍外れてます。でも良いよ良いよ、良いよね~?
私も買っちゃったんです、つい先日。
このハミングバードのチャームが可愛くてさ。
シルバーはすぐ酸化して黒ずむから嫌なんだけど。
髪ゴム?ショートボブで結ぶ髪ないけど。
チバのサインの刻印がなきゃ、チバデザインじゃなきゃ買わないけど。
去年一度は踏みとどまったんだけど。
でも良いよ。人生一度だ。そしてもう先はそんなに長くないぞ。
へらへら幸せにしてくれるんだから、良し!!
しばらくブレスレットでこのまま使って、そのうちゴムを革に替えよう。
あ~眺めてるだけで気持があがる♪
ね?ありすさん♪
「カフカはなぜ自殺しなかったのか?」
2021年11月16日 読書 コメント (2)
このところ、僕は自分についてあまり書き留めていない。
多くのことを書かずにきた。
それは怠惰のせいでもある。
しかし、また心配のためでもある。
自己認識を損ないはしないかという心配だ。
この心配は当然のことだ。
というのも、書きとめることで、自己認識は固まってしまう。
それが最終的な形となる。
そうなってもいいのは、書くことが、
すべての細部に至るまで最高の完全さで、
また完全な真実性をもって行われる場合に限られる。
それができなければ
――いずれにしてもぼくにはその能力はない――
書かれたものは、その自立性によって、
また、かたちとなったものの圧倒的な力によって、
ただのありふれた感情に取って代わってしまう。
そのさい、本当の感情は消え失せ、
書かれたものが無価値だとわかっても、すでに手遅れなのだ。
<1911年1月12日のカフカの日記>
観て思ったこと、聴いて揺れたこと、触れて感じたこと、湧いてくる感情をなんとか書きとめたいと思うけれど、いつもいつもなにか言葉が違うと思う。
カフカでさえそうなんだ。いや、だから名を残すような作家なんだね。
――というか並べて言うことすらおこがましいの極みだ(汗)
「食べることと出すこと」が面白かったので、頭木弘樹の本を。
このカフカの言葉のあとに「言語隠蔽」という現象に触れている。
言語化することで、とても多くのものが抜け落ちてしまううえに、言葉で固定されたイメージだけが残ってしまい、元の像とはかけ離れたものになってしまいがちだという現象。
たとえば犯罪の目撃者に写真を選んでもらう時に、どんな顔をしていたか言葉で説明してもらったひとと、言語化なしで写真を見てもらったひとでは、言語化した人の正解確率がかなり下がる、とか。
恋人のどこが好きなのかを言葉で説明させると、説明しなかった(できなかった)カップルより半年後に交際続いている確率が低かった、とか。
いつもここに向かって言葉にしたい、言葉にしたいと悶々としているけれど、大事な核心に触れそうな部分ほど言葉にならないというのは実感してて(語彙が足りない、というのはもちろんなんだけど)、ただ、その名付けようのないもの、淡々(あわあわ)としたところが、心の、魂の、ふくよかさなのかな。
強いエネルギーをもった太陽の光があたると、消えてしまう朝霧のような。
この本にしても、なぜカフカが自殺しなかったのか、はっきりと結論を述べているわけではない。
けれどこれを読んでたら。
言葉に絶望しながらそれでも小説を書かずにはいられなくて、書き上げては「ここには本物の感情はない」とまた絶望し、出版の機会が訪れても「出版したくない」と本気で思い、繊細で、仕事にも結婚することにも、書くことにさえも絶望し続けて、その絶望を膨大な日記、手紙に書かずにはいられなかった面倒くさいひとカフカが、いらいらハラハラしながら、だんだん愛おしくなってくるのだ。
カフカが並外れた作家だったから、ここまで絶望と格闘する思いを書き続けることができたわけだけど、この矛盾に満ちて優柔不断で逃げ惑う心情は、誰の中にもあるように思う。たいていのひとは、悩み続ける苦しさに無理やり決断したり、うっちゃったりするのだけど。
絶望を手放さない才能、というのがあったのだなぁと思う。
絶望とがっぷり四つに組むんじゃなくて、勝負にでられぬまま逃げ惑いながらも土俵を割らない、みたいな。
呆けてるんじゃなく惚けてるってことで。
2021年11月15日 チバ コメント (2)仕事終わって耳にイヤホン突っ込んで駅へ。
11月に出たチバのCDが良くて。
新曲4曲に、今年のツアーからライブ音源を4曲。
夏にアルバムも出て、そこにも「ああ、最高」と思う曲あったのに、このCDにも胸にくる曲がある。どうしてこんなに「最高」を毎回更新できるんだろう。
チバは、曲以外で、歌うこと以外で何かを語ることはしない、できないひとだけど、彼の歌を聴いてると2020年、2021年の東京の、同じ時空を生きてるんだな、一緒にいるんだなと感じるよ。涙。
そして炸裂するあの声のフレアに魂なぎ倒される。それが快感。
なにもかもが吹き去られる。
・・・・・
大音量でチバ聴きながら買い物して電車に乗ろうとしたところで、駅ビルのトイレにスマホを忘れたことに気づく。
あ~あとため息つきながらトイレに戻り、そこにないこと確認してビルの管理室へ。スマホは出てくると日本のひとを信頼したとおりに届けられてて。サインして、ありがとう、お手数かけました。
電車に乗って帰路。ながらスマホはやめなさい、スマホはそこら辺に置かないでバッグへ入れなきゃだめじゃんと反省つつ、あ~チバが吠えてる~やばいやばいこの声はやばい~と聴き惚れる。
いったいなんなのこの男は、なんなんだこの声はぁぁぁとへらへらして、ふと気づくと降車駅通り過ぎてた。
あららら。
ボケボケの自分が笑えてしまった。
こういうボケにはそーとーイラついてたもんなんだけど、スマホ取りに行った時も電車乗り越したときも、気持はささくれることなく、笑えたから良い。
呆けたんじゃなくて、チバの声に惚れて惚けてるんだからシアワセじゃん、と思えて。
ああ、チバ声にいろいろいろいろ救われてるなぁ。
こういうのを性懲りもなく、というのか。
2021年11月13日 Memorandum2年前の悪夢再びかと思うような出来事があり。
前回の時ほどの寝耳に水感はなく、面倒なことになる前にすんだのだけども。
だけど、ほんと信じられない。
一度ならず二度までも近寄ってくるひと。
弁護士沙汰になっても懲りないひとたち。
善意を装って。
あの懲りなさ、しつこさ、図々しさ、、、大阪のほうのガラの悪いあの政党のひとたちとイメージがダブル。
今回は、弁護士に頼むほどの話ではなかったのだけど、あまりに不愉快だったし放っておいたらまた同じことされかねないと思い――――
https://www.somu-lier.jp/column/contents-certified-mail/
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
つぎ出すようなことにはならないで欲しいけど、メモ代わりに。
ひととひとのトラブルなんて得てして「言った」「言わない」になるので、意志をきっちり伝えて、「伝えた」ってことを第三者に担保することができる郵便局の制度。
弁護士はあんがい簡単に雇えるとか、内容証明付き文書はこんな風に作るとか、あの方々のおかげで、いろいろ勉強させてもらってる。
腹立たしいことには変わりないけれどもなっ!
こうして私は無口になってゆく
2021年11月13日 日常 コメント (2)――洗濯終わったあとの排水ができなくなってる。洗濯機の排水弁が開かなくなっちゃってるっぽい。電話して修理、頼むね。
――排水管や水道工事は、怪しいとこ多いから地元で探したほうが良いね。
――( 洗 濯 機 の 排 水 弁 の修理だっちゅーの)
・・・・・
――いつものカレンダーがみつからないのよ。探して見るけど。
――去年、余分に買っておけばよかったんだよ。
――(今探してるのは22年の暦だっちゅーの)
なんかもう、意味不明に脱力するんだけどぉ。
お父さんに帰ってきてほしいなぁ。。。
Qu’est-ce que c’est ?
2021年11月11日 庭 と 草、花、樹 コメント (2)夏から冬、うちの前を歩くひとたちが発する疑問が Qu’est-ce que c’est ?
今の時季は黄色く色づいた実が、ちょうど大人の顔のあたりにぶら下がっているので目につくらしい。
年長さんくらいの娘の「これ、なーに?」に、お父さん「ん~~~~~ 梨かな?」
部屋で聴いてて「ちがう~~(笑)」となる。
ともかく大きくて形もしもぶくれのドロップ型なので、いままで正解にたどり着いたのを聞いたことがない。
今日は、通りかかった老婦人おふたりが Qu’est-ce que c’est ?
カリンじゃないの? そうかしら? カリンよ、きっと。
落ち葉を掃いていた私に気づいて話しかけられる。私もたまには正解を言いたいので庭にいて良かった。
正解は Citron です。
そういえばカリン、そろそろ熟して落果してる頃かも知れない。
貰いに行かなくては♪
昨日、読書館で読み終えたのはこれ。
初めての子の出産を迎えるパリの夫婦と真っ赤な観賞魚ベタ
メキシコシティの閑静な住宅街の伯母の家に預けられた少年とゴキブリ
飼っている牝猫と時を同じくして妊娠する女子学生
不倫関係に陥った二人のバイオリニストと菌類
パリ在住の中国生まれの劇作家と蛇
読みながら感じていた、生理的な嫌悪感――嫌悪と言うほどネガテエィブなものではないのだけど、肩のあたりの産毛がちいさく波立つくらいの――があって、それが文学的なカタルシスに繋がっているんだけど。
この感じってペドロ・アルモドバルの映画を観た時に感じる薄い気持ち悪さと似てるなぁと思った。
それと橋本治の「蝶のゆくえ」を読んだときの読後感とか。
グアダルーペ・ネッテルは1973年メキシコシティ生まれの女性作家。
いまや、小説家の性をわざわざ記すのはフェミニズム的にどうなの?って時代になってきてるようには思うけど、作品が女の生理を抜きには描けない世界だからどうしても作家の属性に目が行ってしまう。
性と生殖の、因果の98%を担わざる得ないいきものについては、日本の<女流>作家の書いたものよりネッテルの短編の方が好ましい、かな?
同じように感じた橋本治とネッテルにどういう共通項があるのかわからないけど。
女の生理との距離感かなぁ? 昇華の度合い?
よくわからない。
でも、読めて良かったなとおもう作品群。
メキシコ人作家の作品ってはじめてかも。