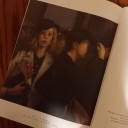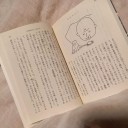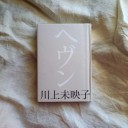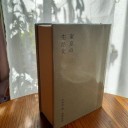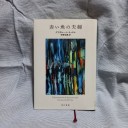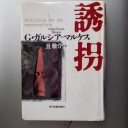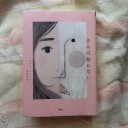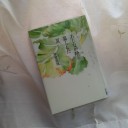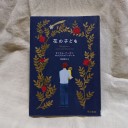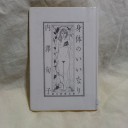私の短編が初めて売れたのは1957年のことだ。だから私はこの仕事を60年続けてきたことになる。それももうできなくなるかもしれない。このところよくそう思うようになり、少なくとも長編に関しては数年まえからはもう無理かもしれないと思っている。実際にはそう思いはじめてからも、ニ、三冊出してはいるが、次の一冊はもう期待していない。短編と中編は今でも書いている。私にあとどれほどの時間が残されているにせよ、今後も書けるかもしれないし、もう書けないかもしれない。
それはそれでかまわない。 <序文より>
ローレンス・ブロックが編んだ「短編画廊」と同じコンセプトの短編集。
「短編画廊」に収められたブロックの「オートマットの秋」が良かったので今回も楽しみだったのに。というかブロックの短編をこそ読みたくて手に取ったのにな。
ラファエル・ソイヤー「オフィス・ガール」
なかなかそそる絵でしょ。映画「チャイナタウン」のフェイ・ダナウェイのような面差しの女性の絵。ドラマを秘めた表情。ブロックのミステリで読みたかったな。
1000Wordくらい書いて、もうどこにも着地できないと思ったらしい。
「作品を提供できなくなっていた」
「私はもうお役ご免なので」
「私は駄目だったけど」
7ページに及ぶ序文で何度もなんども。
ああ、もうほんとうにスカダーの新作は読めないのかなぁ。
寂しいなぁ。
今後も書けるかもしれないし…期待するにはあまりにも頼りない言葉だなぁ。
今年84歳になるのだものなぁ。
……なんだかなぁ。
目玉焼きのつづき。
「家族ゲーム」の目玉焼きちゅうちゅうは1968年にでた「女たちよ!」の中の一編で「目玉焼の正しい食べ方」として書かれてる。
……というのをWikiで読んで、「女たちよ!」をひっぱりだす、、、つもりが見つからずAmazonで買う。この本買うのこれで3回目。あ、友人の娘に買って渡したことあるから4回買ってるのか。あ、違う?持ってたのをあげちゃって、また読みたくなって買って、引っ越しでどこ行ったか分からなくなり、、でやっぱり3回目か、そっか。
もとは文芸春秋からでてたんだけど、今回買ったのが2005年に新潮からでたもので、池澤夏樹の解説が読めて良かった。知って買ったわけじゃなくて、たまたま安かったからなんだけど。
それだけ買い直してるのに、内容をあまり(ほぼ?)覚えていない。
ただ初めて読んだとき、大学生の終わりごろだったけど、大人になりたいと思い大人になろうとしている都下育ちの戦後核家族の庶民の娘に、憧れてみる甲斐のある大人的なスタイルを見せられたんだろうと思う。
いま読みかえして。
アル・デンテとかアボカドとか、いまならだれでも知ってる。
フランスパンは青山5丁目のピーコックが美味いとか、いまなら言わないだろう。
(いや、3周くらいまわってやっぱり青山ピーコックなのかもしれない。スタイルとして、そういう方がツウだと思われるのかもしれない)
で、だから古びてるのかというと、そんなことない。
3回買って読んでも面白いって言うのは、すごいことかもしれない。
これが書かれてから50年以上経ってる。
これを書いた30代前半の伊丹十三の年齢を大きく越えてるけど、ここに書かれてることのいろいろが身につかぬままだ。
伊丹十三という才能。
彼が身につけてきた教養っていうのは生まれ育ち、資産の後ろ盾あってのことではあるけれども、伊丹十三だから身についたのだと言えるし。
軽い、ユーモアにあふれたエッセイ、と今読む人は思うかもしれない。ちょっとキザで嫌味、と感じる者もいるだろう。よくある本だよ、これは。
たしかに、この種の文章に出会うことは珍しくない。しかしそれは今だから言えることであって、最初に刊行された1968年にはこれはまったく新しい、挑発的な、驚くべき本だった。ぼくたちは一種まぶしいものを見るような思いでこの本を手にした。笑って読み、膝を打ち、あこがれ、勇気づけられた。
なにがそんなに新しかったのか?まずは自信に満ちた個人主義、趣味を中心に据える人生観、食物や酒や車についての粋なセンス、(つまりは)消費の喜び、ヨーロッパを起点にしたホンモノ指向。 池澤夏樹:解説より
この本が世に出て半世紀過ぎたけど、伊丹十三に追いつく人はいたかな。
パルジャミーノやニース風サラダくらいは覚えたかもしれないけど、それだってホンモノではないかもしれないのが悲しい。
この本の中で、流行が循環するサイクルについて服装学者ジェイムズ・レイヴァというひとが
10年前は 下品
5年前は 恥知らず
1年前は 大胆
当時 スマート
1年後 みすぼらしい
10年後 醜悪
20年後 噴飯もの
30年後 滑稽
50年後 風変わりな
70年後 魅力的
100年後 ロマンチック
150年後 美しい
と言ってる(と紹介されてる)けど、なるほどなぁと。エッセイなんかにも当てはまるかもしれない。
20世紀中はこの本もスノッブと思うひともいたかもなぁと思う。友人の娘にあげた頃なんて、もしかしたら一番ピンとこなかったかもしれないなぁ。
でも50年たったいま、風変わりでカッコいい大人がいたんだなぁと読まれるかも。
1000年後くらいには、「徒然草」や「枕草子」並みの随筆として読まれるかもしれない。
あ、そうそう、目玉焼の正しい食べ方。
「彼は皿に口を近づけて、真ん中の黄身を、ぺろりと吸いとってしまうのですが、こんなことが人前で許されるべきものではありません」
映画「家族ゲーム」の目玉焼きちゅうちゅうは伊丹十三の存在なくしては許されない絵面ですね。
コジマが「ヘブン」と名付けていた美術館の絵を観たい。
読みながらシャガールの絵が浮かんだんだけど。
まったく架空の絵かもしれないけど。
夏休みの最初の日に、美術館へ出かけ、美術館にそそぐ明るい陽ざしを浴びてベンチに座り、ひと房の髪を切る、その時間で終わればいいのにと思った。
静かなHさんとソノさんを足して0.7掛けるくらいにすると「るきさん」が出来上がりそうな気がするなぁ。
「10年後のるきさん」が追加されてる新装版が読みたくて手にとったけど、う~ん、高野文子は面白いなぁ。
1988年から1993年までの連載だから、え? 30年も前のマンガなの?
「るきさん」という女のひとのキャラクターがもともとレトロ風味だし、人物のエピソードは古びないんだよねぇ。逆に90年前後ってこんな風俗だったっけって見えてくるとこ面白い。駅の券売機で小銭入れて切符買ってるんだーとか、この頃のバーゲンシーズンってこんなだったなー景気良かったんだなーバブルだもんねーとかとか。よく見たら表紙の背景がバーニーズニューヨークだし。
高野文子の、ああもうこれはブンガクだわという作品群も好きなんだけど、「るきさん」や「ラッキー嬢ちゃん」みたいな軽やかなタッチのマンガ好きなんだよねぇ。「るきさん」続き描かないかなぁ。還暦るきさん(笑)
今度、Hさんに訊いてみよう。高野文子、読みます?って。たぶん読んでると思う。すくなくとも知ってる。ソノさんはきっと知らない(笑)
「目の見えない白鳥さんとアートを見に行く」
2022年1月16日 読書*第1章 そこに美術館があったから
Life goes on.
――これ以上要約のしようのない想い。
お互いの体の機能を拡張し合いながら繋がれるということ
――何の話だったかな。「感覚」の実験のようなこと。目隠しをしてアテンドしてもらいながら砂浜(が望ましい)を歩いてみる。やってみたいな、と思ったんだけど。
「セラピスト」を読んだ後だったか。
彼は「わかること」ではなく、「わからないこと」を楽しんでいる
――読み始めてすぐに、目の見えない人に説明するのだからアテンドの語彙力とか言葉の解像度が重要になるのかな、と思ったけれどそうではない。
無知であることはいいことである。バイアスなく、ただ無心に作品と向き合える
――ちょっと私の音楽の聴き方がそうだ。
色は概念的に理解している
それぞれの色には特定のイメージがあって、それを(視覚ではなくその特徴的なイメージで)理解している
――白鳥さんの「描く」「描き直す?」ゴッホを見てみたい。
と思うのは、「視覚」にとらわれ過ぎてる?
*第2章 マッサージ屋とレオナルド・ダ・ビンチの…
自分には、目が見えないという状態が普通で“見える”という状態がわからないから“見えない人は苦労する”と言われても、その意味が解らなかった。
――「目が見えないなんて大変だなぁ」という先入観、偏見、、、私にもあったかも。あるな。これって、想像力がないよねぇ。。
自分が普段使っている感覚、センサーを手掛かりに世界の理解を組み立ててるから、通常モードだとそうなってしまう。そのひとがどんな感覚を駆使してるのか。齋藤陽道さんの本やTweetみても驚くことがいっぱい。五感揃ってるから高い感受性をもってるとは限らないね。
自動音声の抑揚のない声、早送りしているようなスピード。
――感情過多ではないほうがすっと脳に入る?
*第3章 宇宙の星だって抗えないもの
ボルタンスキ―回顧展
――https://momijimomiji.diarynote.jp/201908010147547171/
ボルタンスキー、去年の夏に亡くなったのか。
人間は多くのものと闘えるけれど、時を相手には闘えない(ボルタンスキー)
*第4章 ビルと飛行機、どこでもない風景
彼はその言葉にならない「間」すらも愛する。思わず漏れ出す「ああ……」というため息のなかにもさまざまな思いが流れその即興の音色を楽しんでいる。
――気配。DIDに参加した時。手を繋ぐことや声、言葉が視覚を補完したのは確かだけど、みなで立ち止まっている時に、隣のひとが背を向けたとか、こちらに顔を向けたとか、微かな息遣いと衣擦れくらいのこそりとした気配すら感じ取れたのを思い出した。
911の跡地。モニュメントとショッピングモールとオーディオアーカイブ。
――911の跡地の再開発のコンペ。安藤忠雄が提案した「地球の表面を模した芝の緩やかな台地」が記憶に残っている。結局は「NYCのスカイラインを元通りにしなくてはテロに打ち勝ったことにならない」的な意見が多数で、今のような超高層ビルになったという、アメリカらしいなと思ったの思い出した。日記に書いたと思うのだけど、どこ?
オーディオアーカイブ、聴くとしたら準備が要るだろうな。豊島の心臓音ですら、眩暈がしたし心臓が早くなるのを感じたから。911の音声をサラウンドで。想像するだけで首の両側がきゅううっとなる。
ビルと飛行機、となったらどうしても911を思い出す。テレビ画面の中の、強烈な映像記憶。見た。見た?あれはほんとうに見た、のか?
*第5章 湖に見える原っぱってなんだ
目の見える人も、実はちゃんと見えていない
セレクティブ・アテンション 認知バイアス
眼は意味あるいは記号に感応しているのであって、そこから「見る」ことの野生は脱落している(鷲田清一「想像のレッスン」)
「印象派」
――印象派の絵。なんとなく当たり前に見慣れてしまっているので、光を描く技法の革命といわれても、へぇーそーなんだーへぇー。好きか嫌いかっていったら、特に?別に?部屋に飾ろうとは考えないかな。
*第6章 鬼の目に涙は光る
*第7章 荒野をゆく人々
*第8章 読み返すことのない日記
ヂョン・ヨンドゥ 地上の道のように
2014年11月8日[土]~ 2015年2月1日[日]@水戸芸術館現代美術ギャラリー
https://www.youtube.com/watch?v=dUz8X_t3ohY
ワイルド・グース・チェイスの動画あり。フルで観てみたい。
ピアノ・小曽根真
wild goose-chase 無駄な追跡 捕まえられないものを追いかける
*第9章 みんなどこへ行った?
――ディスリンピック2680が見たいのだけど、図書館の本なのでカバー裏を見ることができない。
*第10章 自宅発、オルセー美術館ゆき
哲学者の青山拓央、著書の中で「すこし恥ずかしいのだが、あまり共感を得られないであろう自分の癖をひとつ書いてみる。日常生活の中でふと、周囲に聴こえないくらいの声で『今』とつぶやく癖を私は持っている」と告白する。
「その作業において、私はいわば、自分の人生に時間的なしおりを挟んでいる。ここまで読んだというしるしで本にしおりを挟むように、ここまで生きたというしるしで人生にしおりを挟むわけだ。そんなことがわざわざ必要なのは、人生全体をどこまで生きたかがなんとなくボンヤリしているからだが…」(「心にとって時間とは何か」)
――第8章で白鳥さんが「読み返すことのない日記」のように写真を撮り続けていることを思い出す。シャッターを押すことで『今』のしおりをはさんでいるのではないか。
249pの言葉を書き写してから白鳥さんのカメラについて書いたけど、数ページあと252pに同じこと書いてあった。(読みながらメモしてる)
白鳥さんがバーチャル鑑賞に興味を示さないだろうことはわかりきってたんじゃないかな。第4章で抜き書きした部分からも分かる。著者もわかってないはずない。敢えて書いてるんだろうけど、この章はちょっとあざとい。コロナで美術館という空間を共有することが難しくなった時期だから、な。
彼はかなり本気で「いま」ここにいる「自分」しか確かなものはないと感じているのかも知れなかった。
――5分間宇宙のこと、時間は未来から過去へ流れるという物理理論、時間の記憶、過去の書き換え。
ほんとうに「今」だけなんだよなぁ。バーチャルじゃダメだって、この2年で良くわかったよ。2年前の春先から、ライヴの配信をやるアーティストも増えて、初めは観て慰められたような気にもなったけど、いつの間にか観なくなってた。
場の力って替え難い。たとえ表情も見えない2階席からだったとしてもそこに、今、チバがいるってことは絶対。たとえ会話はしないようにしたとしても目の前に友がいるならそれだけで場の空気は違う。
「存在」ってイコール「今」なのか。
*第11章 ただ夢を見るために
22年もの間、ふたりはこの日を夢見ていたのだろうか?
2010年ニューヨーク近代美術館・MoMA マリーナ・アブラモヴィッチ
――目の前にいる、とは、こういうことだ。
*第12章 白い鳥がいる湖
白鳥さんが幸せを感じる時ってどんな時?
その幸せはどこにあると思う?
――うん。うん、ほんとに。
……………トリアエズ、オシマイ。
自立する本、一冊。
岸政彦は「断片的なものの社会学」を読んでから気になってるひと。
ここに感想書いたような気がしてたけどみつからないなぁ。
たぶん、「断片がさらに粉々になってしまって掬い上げられないんだけど、その断片のひとつひとつが好ましく思える」みたいなこと。
そもそも社会学ってなんだろう。
私も大学の専攻が社会学カテゴリだったのだけど、社会学ってなんでもありというか。素材見つけてどう輪郭を切り出していくか、彫刻家とか編集者とかに近いような?
150人の聞き手と150人の語り手による東京に生きる人たちの断片を集めた「生活史」
面白そうだなと思って図書館に予約して、届いてびっくり。1200ページ。辞書か?
運よく正月休み挟んで3週間借りられたけど、読み切れる気はしない。一気読みするような本でもないから、ぱらぱらいきましょう。
「カフカはなぜ自殺しなかったのか?」
2021年11月16日 読書 コメント (2)
このところ、僕は自分についてあまり書き留めていない。
多くのことを書かずにきた。
それは怠惰のせいでもある。
しかし、また心配のためでもある。
自己認識を損ないはしないかという心配だ。
この心配は当然のことだ。
というのも、書きとめることで、自己認識は固まってしまう。
それが最終的な形となる。
そうなってもいいのは、書くことが、
すべての細部に至るまで最高の完全さで、
また完全な真実性をもって行われる場合に限られる。
それができなければ
――いずれにしてもぼくにはその能力はない――
書かれたものは、その自立性によって、
また、かたちとなったものの圧倒的な力によって、
ただのありふれた感情に取って代わってしまう。
そのさい、本当の感情は消え失せ、
書かれたものが無価値だとわかっても、すでに手遅れなのだ。
<1911年1月12日のカフカの日記>
観て思ったこと、聴いて揺れたこと、触れて感じたこと、湧いてくる感情をなんとか書きとめたいと思うけれど、いつもいつもなにか言葉が違うと思う。
カフカでさえそうなんだ。いや、だから名を残すような作家なんだね。
――というか並べて言うことすらおこがましいの極みだ(汗)
「食べることと出すこと」が面白かったので、頭木弘樹の本を。
このカフカの言葉のあとに「言語隠蔽」という現象に触れている。
言語化することで、とても多くのものが抜け落ちてしまううえに、言葉で固定されたイメージだけが残ってしまい、元の像とはかけ離れたものになってしまいがちだという現象。
たとえば犯罪の目撃者に写真を選んでもらう時に、どんな顔をしていたか言葉で説明してもらったひとと、言語化なしで写真を見てもらったひとでは、言語化した人の正解確率がかなり下がる、とか。
恋人のどこが好きなのかを言葉で説明させると、説明しなかった(できなかった)カップルより半年後に交際続いている確率が低かった、とか。
いつもここに向かって言葉にしたい、言葉にしたいと悶々としているけれど、大事な核心に触れそうな部分ほど言葉にならないというのは実感してて(語彙が足りない、というのはもちろんなんだけど)、ただ、その名付けようのないもの、淡々(あわあわ)としたところが、心の、魂の、ふくよかさなのかな。
強いエネルギーをもった太陽の光があたると、消えてしまう朝霧のような。
この本にしても、なぜカフカが自殺しなかったのか、はっきりと結論を述べているわけではない。
けれどこれを読んでたら。
言葉に絶望しながらそれでも小説を書かずにはいられなくて、書き上げては「ここには本物の感情はない」とまた絶望し、出版の機会が訪れても「出版したくない」と本気で思い、繊細で、仕事にも結婚することにも、書くことにさえも絶望し続けて、その絶望を膨大な日記、手紙に書かずにはいられなかった面倒くさいひとカフカが、いらいらハラハラしながら、だんだん愛おしくなってくるのだ。
カフカが並外れた作家だったから、ここまで絶望と格闘する思いを書き続けることができたわけだけど、この矛盾に満ちて優柔不断で逃げ惑う心情は、誰の中にもあるように思う。たいていのひとは、悩み続ける苦しさに無理やり決断したり、うっちゃったりするのだけど。
絶望を手放さない才能、というのがあったのだなぁと思う。
絶望とがっぷり四つに組むんじゃなくて、勝負にでられぬまま逃げ惑いながらも土俵を割らない、みたいな。
昨日、読書館で読み終えたのはこれ。
初めての子の出産を迎えるパリの夫婦と真っ赤な観賞魚ベタ
メキシコシティの閑静な住宅街の伯母の家に預けられた少年とゴキブリ
飼っている牝猫と時を同じくして妊娠する女子学生
不倫関係に陥った二人のバイオリニストと菌類
パリ在住の中国生まれの劇作家と蛇
読みながら感じていた、生理的な嫌悪感――嫌悪と言うほどネガテエィブなものではないのだけど、肩のあたりの産毛がちいさく波立つくらいの――があって、それが文学的なカタルシスに繋がっているんだけど。
この感じってペドロ・アルモドバルの映画を観た時に感じる薄い気持ち悪さと似てるなぁと思った。
それと橋本治の「蝶のゆくえ」を読んだときの読後感とか。
グアダルーペ・ネッテルは1973年メキシコシティ生まれの女性作家。
いまや、小説家の性をわざわざ記すのはフェミニズム的にどうなの?って時代になってきてるようには思うけど、作品が女の生理を抜きには描けない世界だからどうしても作家の属性に目が行ってしまう。
性と生殖の、因果の98%を担わざる得ないいきものについては、日本の<女流>作家の書いたものよりネッテルの短編の方が好ましい、かな?
同じように感じた橋本治とネッテルにどういう共通項があるのかわからないけど。
女の生理との距離感かなぁ? 昇華の度合い?
よくわからない。
でも、読めて良かったなとおもう作品群。
メキシコ人作家の作品ってはじめてかも。
「ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集」
2021年10月28日 読書
きりん
きりん
だれがつけたの?
すずがなるような
ほしがふるような
日曜の朝があけたような名前を
ふるさとの草原をかけたとき
いっきに100キロかけたとき
一ぞくみんなでかけたとき
くびのたてがみがなったの?
もえる風になりひびいたの?
きりん
きりん
きりりりん
きょうも空においた
小さなその耳に
地球のうらがわから
しんきろうのくにから
ふるさとの風がひびいてくるの?
きりん
きりん
きりりりん
「 きりん 」 まどみちお
き り ん という音。
哺乳綱偶蹄目キリン科キリン属の偶蹄類と分類されて名付けられる以前。
あの首の長い黄色に茶色のだんだら模様の、優しい大きな目をしたどうぶつは
き り ん き り ん き り り り ん
と鳴りながらそこにいたんだねぇ。ふふふ。
・・・・・
意識して詩を読みに行くということがあまりないので、うん、こういう本も良いなぁと思う。
高野文子の「るきさん」の新装版がでて、そこから高野文子が挿絵を描いているこの本にたどり着いた。創作童話、というくくりなのかな。
先日の高階杞一の詩もこの本に載っていた。
「ぼく」は「きみ」に詩集を手渡す。
「ここんとこ、読んでみな」と言って。
きみは、あっというまに、おとなになる。
そして、さまざまなことを、わすれてしまう。
この夏におこった、わすれたくないことも。ふたりで読んだ詩も。
大人になってからも忘れてばっかりだ。
「きりん」を読みながら、幼稚園のときにキリンの絵を描いたことを思い出した。ピンクの画用紙に、黄色いキリンをクレヨンで描いた。その絵はアルバムの表紙に加工されて卒園の記念にもらったのだった。気に入っていて、結構大きくなっても持っていたと思うのだけど、さすがに今はもうない。取っておけばよかったとまでは思わないけれど、ほらね、いろんなことを忘れて捨てて生きている。
マルーハ・パチョンとアルベルト・ビヤミサル夫妻は一九九三年の十月、六か月におよぶ彼女の誘拐中の経験と、彼女を解放させるまでに夫がたどった経緯を本にまとめたらどうかと私のところに話をもちかけてきた。草稿がかなり出来上がった段階で、私たちは、彼女の事件と、同時期にコロンビア国内で起きていた他九件の誘拐事件とを切り離して扱うわけにはいかないのに気づいた。本当のところ、これは別個の誘拐事件が十件並行して起こっていたのではなく――最初はそう思われたのだが――、きわめて巧妙に選ばれた十人の人間がひとつの集団として、ひとつの誘拐団によって、たったひとつの目的のために誘拐された事件だったのだ。 (ガルシア=マルケスによる冒頭の謝辞)
実は、この冒頭の謝辞もガルシア=マルケスの仕掛けなのだ――と言われたらきっと信じてしまう。
はぁ~物語ることの巧みさ、息つく間もなく読み進めてしまった。
ルポルタージュの棚にガルシア=マルケスの名前を見つけて手にとった。本文の始まり、マルーハが誘拐されるシーンは映画のように画が浮かんだ。なにこれ、面白い!とその場で検索して、「犬の力」のリアル版とわかる。「犬の力」を読んでいたおかげで、複雑な背景がだいたいわかって迷子にならずに読めた。
事件の背景としては一九八〇年代の世界を席巻した大コカイン・ブーム、それによって急激に力を強めた密輸組織メデジン・カルテル、膨大なコカイン・マネーの急激な流入によるコロンビア経済の社会の混乱、メデジン・カルテルによる市場の独占に反発するその他の組織との抗争の激化、アメリカの圧力による取り締まり強化とその反作用としてのテロ事件の多発、治安の悪化による市民の不満を受けてコカイン密輸組織との対決姿勢を明確にした若い熱血大統領の当選、といった生の現代史がある。
・・・中略・・・
一九九〇年という年は、当選したばかりのガビリア大統領が、武力による摘発には限界があり、かえってテロの激化を招くという現実を前にして、密輸組織の投降を促すための司法取引の可能性を模索していた時期にあたる。つまり、投降して自分の犯罪を認めた者は法的に優遇する、と確約することによって、テロの収束と組織の解体を狙ったのである。取引の内容とは、海外(つまりアメリカ)からの犯罪者引き渡し請求に応じない(つまり、投降した者は量刑が累積されるアメリカではなく、一番長い刑のみが執行されるコロンビア国内で割引された刑に服する。一方、投降せずつかまった者は容赦なくアメリカに引き渡す)、本人および親族の安全を保障する、刑に服する場所、条件等に付いて交渉の余地を残す、などだった。
これらの優遇措置はすべて、究極的には、アンティオキア県の首府メデジンに本拠を持つ密輸組織、通称メデジン・カルテルの首領であるパブロ・エスコバルの投降を促すために検討されたものだった。 (訳者あとがき)
現代の日本で「誘拐」と言われてイメージするのと次元が違い過ぎる。
日本だったら戦国時代の話みたいだ。
司法取引の内容が桁違い。
法律を変えさせ、防衛大臣や警察庁長官を更迭させる。収監される場所は“刑務所”という名の宮殿。
誘拐された人たちというのは、この取引に見合う価値のあるひとたちだった。
マルーハの出自は代々著名な知識人を出した家系で、国営映画産業の取締役。救出に奔走する夫は国会議員。ほかに元大統領の娘で著名なジャーナリストとか。
この時誘拐された10人は8人が解放されて、エスコバルは投降し宮殿に移り国家に保護される。誘拐されていたひとたちは、よくぞ生き抜いたと思うし、救出までのやり取りは緊迫感があって、まあほんとにこの夫妻を主役にこのまんま映画にすれば、ハリウッド的ハッピーエンドだ。
エピローグの最後の最後に語られるシーンは、いや、いつかどこかのサスペンス映画で見たかもよ?と思うようだし。ここは、エスコバルの力を見せつけるようでゾッとしたし、ガルシア=マルケスのエンターティメントな物語力にも感心する。
これはノンフィクションです。
そして。
「誘拐」読みながらずっと思い出していた「犬の力」
ドン・ウインズロウは、「この取引に見合う価値のあるひと」ではないひとたちを描いていたなぁ、と。
「誘拐」でも解放の駆け引きの途中でたくさんひとが死んでいる。誘拐の現場で射殺された運転手、車のトランクで発見された弁護士、自動車爆弾で吹き飛ばされた数百人。
それからカルテルに関わることでしか生計を立てられない底辺のひとたち。
ウインズロウがこの本を読んでないはずはないと思うので、「誘拐」のメインストーリーでは触れられなかったひとたちの人生が心に残ったんだろうなと思う。
ともかく。
「誘拐」面白かった。
「食べることと出すこと」
2021年8月5日 読書 コメント (2)サイドテーブルにカップが置かれた。
手にとってみると、温かい透明なスープが注がれていた。
え?これ飲んで良いの?もう?
恐るおそるカップに唇をつけて舌先をスープに触れる。
唇をなめるようにして味を確かめる。
人生で一番美味しいスープを味わった瞬間。
32歳だった。
少しずつすこしずつ、飲んだ。
鶏のスープかな、具はなにもなく脂も浮いていない。
ほんのりハーブの香りがしたかもしれない。
鶏のエキスだけ。なんて美味しいんだ。
なんて美味しいの。さすが美食の国。
飲み干した。
前日、虫垂炎の開腹手術をしていた。
術後24時間は経っていたけれど、こんなに早くスープがでるとは、日本とは違うんだなと思ったけど、言葉が通じないので確かめようもなくなすがまま、出されたのなら飲んで良いのだろうと思ったのだった。
数分後。
まだ余韻を味わっているくらいの、後。
なんの前触れもなく生温かい液体が身体から外に出てシーツを濡らした。
ほんとにほんとに、ほんと~うに。まったくnothing。
排泄するよ~というサインのようなものは一切なかったのだ。
このとき私の身体は外界に向けて開いている一本の管だった。
入れたものは出る。それだけだった。
人間には口から肛門までのトンネルがある。そこを食べ物の電車や車やバイクが通過していく。いいものも悪いものもまきちらしながら。
そんな物騒なものが、身体の中心にあいているのである。
その穴は、外界に通じている。胃腸は外界に通じているのだ。
ゆらゆら帝国というバンドの『空洞です』という曲を聴いたとき、
「俺は空洞」
「バカな子どもがふざけて駆け抜ける」
という歌詞に、ひどくひきつけられた。
もちろん、この空洞というのは、心のむなしさのようなことなのだろうけど、私にはもうそうは聞こえないのだった。
ゆらゆら帝国、私も大好きだ。
まさかここで「空洞です」に言及されるとは思ってなかったけど。
外界に通じる空洞、それ知ってます。
実感したのは幸いにも一度だけだけど。
「食べて出すだけ」の人生は……なんて素晴らしいのだろう!
「飢えから、栄養不足による飢えを引いたもの」を体験した人はあまりいない。
点滴によって栄養は足りているのに、「喉」は何かを飲み込みたいと言い、「顎」は犬のように骨の形をしたガムを噛みたいと叫び、「舌」はとにかく味のするものを! と懇願してくるのだと著者はいう。
こうして、食べて出すことがうまくできないと、日常は経験したことのない戦いの場となる。
絶食後に始めて口に入れたヨーグルトが爆発するとは?
茫然と便の海に立っているときに看護師から雑巾を手渡されたときの気分は?
便が心配でひきこもり生活が続いた後、外を歩くと風景が後ろに流れていくとは?
食べて出すだけの日常とは、何かを為すためのスタート地点ではなく、偉大な成果であることが心底わかる傑作。
切実さの狭間に漂う不思議なユーモアが、何が「ケア」なのかを教えてくれる。
<Amazon 出版社コメント>
なにからなにまで interesting な読書でした。
身体(しんたい)というものの不思議を知ってるようで知らなかったな、と。
「私」の主人は、この身体なのだと。頭でっかちになったヒトは精神こそが主で身体はその容れ物くらいにしか考えなくなったけれど、そうじゃないと。
内澤旬子の「身体のいいなり」にも通じるけれど、身体こそが、私の主人なんだなと、改めて。
表紙の写真は齋藤陽道。
著者の五十嵐大が、“ふつう”じゃないことに戸惑っておそるおそる世界を覗いていた子どもの自分が写っていると感じたという写真。
著者の両親はろう者で、耳の聴こえない両親に育てられた子どもを「コーダ」(CODA/Children of Deaf Adults)というのだそうだ。
手話サークルで知り合ったSちゃんという聴覚障害者の女性に、「五十嵐くんはコーダなんだよね」と言われて、コーダという言葉を初めて知りました。耳の聴こえない親から生まれた子どもを指す言葉で、アメリカでは研究が進んでいる、日本だけでも二万二千人のコーダがいる、と知って本当にびっくりしたんです。それまで自分の苦しみは、世界の誰とも共有できないものだと思っていました。でも同じような境遇にある人が、日本だけでもたくさんいる。そう思ったらすごく勇気づけられたんです。まるで人生にぱっと明かりが灯ったような瞬間でしたね。
https://shosetsu-maru.com/interviews/their-window/5
七尾旅人、坂口恭平をゆるくフォローしていて齋藤陽道の名前を知り写真を見て、名前をちゃんと知る前からなんども彼の写真を見ていたことを知る。いまは齋藤陽道がSNSにあげる絵日記が楽しみ。ろうの写真家である齋藤陽道と五十嵐大の往復書簡を何通かネットで読んでこの本にたどり着く。
・・・
映画「ザ・トライブ」を観た頃から手話という表現が気になっている。
手話が伝えてくる世界がものすごく騒々しく豊かであること。手話が単なる発語の補完ではないこと。日本語と日本手話はまったく別の「言語」であること。などなど。
・・・
なんというのだろう。
家族のバックボーンも、自分のアイデンティティ(と思っているもの)も、なにひとつ誰かと同じものなんてないし、世界は広いし、知らないことは膨大だし、下手したら知らないってことさえ知らずに過ごしてしまうし。
でもまあ、だから本は読もう。気になる人はそっとフォローしよう。
と思う。
「JR上野駅公園口」
2021年7月20日 読書 コメント (2)橋本治の「草薙の剣」で語られていた昭和、平成の90年のどこかにカズさんはいたかもしれないと思う。
オリンピック村の建設現場でネコを押していたのがそうかもしれないし、文化会館の軒下に立っていた男が遠景に映っていたかもしれない。
ホメロスが語れない、平和で貧しい時代の退屈で平凡な不幸。
カズさんのカズはきっと昭和の「和」だ。
「おめえはつくづく運がねぇどなぁ…」
そうかもしれない。そうなのかもしれないけど。ただそれだけのことなのかもしれないけど。
一生懸命に、家族のために働き続けていつも疲れて、自分の人生に馴れることのできなかった男には呪いのようだ。
「草薙の剣」を柳美里の業の筆で書くと「JR上野駅公園口」になるのかな。
「草薙の剣」の人生もあまり、いやまったく幸せそうではなかったけど、柳美里はほんとに不幸しか書かないね。
柳美里って、臓腑を絞るような憤りを抱えてる気がするんだけど、たぶん柳美里自身は、それが常態すぎて慣れてしまってるんだろう。だけど、それを浴びる読者はほんとに疲れるよね。
柳美里を読むって、ある意味自虐? そのくらいカタルシスがない。
でも、必ず、書き写しておきたいと思う表現があるのでついつい読んでしまうんだよねぇ。
あ、不幸文学にカタルシスを求めるのは間違いか。
本作は「ホーム」でも「家族」でもない「ハウス」に暮らす個人の話だ。家族の絆を取り戻すようなホームドラマではない。
著者も言っているように「家族小説ではなく、家族の中の個人を書いたもの」であり、「何もかも見せているようで隠し、隠しているようでも真実を見せる個人を、家族というつながりのなかで観察した」物語である。 <訳者あとがき>
「ひとつ屋根の下」という言い回しがあるね。
ひとつ屋根の下<ハウス>に住むのは、家族だろうか?
11歳の少女ユジの失踪をきっかけに、次第に明るみになっていく家族それぞれの秘密。 <新泉社HP>
秘密ってなんだろう。
意識して隠しておきたいものか。知られるわけにはいかないと強く思うものか。それは悪事か。
友達に秘密主義と言われる私だけれど、そんなに悪事は働いてないよ。秘密にしたいと思うことだってたいしたことじゃない。たぶん。
嬉々として他人に言ってまわりたい事柄、考えばかりがそのひとのすべてじゃぁない。
ただ、言わないでいるだけ。言わないでいる、それだけのことが、他人とのかかわりの中で隠し事になって、望まないのに暴かれたりすると「秘密」だったことになる。
サンホ : ソウルで小さな貿易会社を経営している
ウギョン : サンホの妻。韓国華僑。
ユジ : サンホとウギョンの娘。11歳。
ヘソン : サンホの長男、20歳。
ウンソン : サンホの長女22歳。
ミン : 韓国生まれ台湾育ち。ウギョンの元恋人。
たとえばウギョン。
サンホからみれば妻で、ユジからは母で、ヘソンからは義母で、ウンソンからは父の後妻で、ミンからは昔の恋人で。ウギョンはそれぞれとの関係の中で見せている姿がちがう。それは意識してではなく。そんなの誰だってそうだろう。
逆に言えば、誰もがウギョンの一面しか知らないということだ。誰もがみんなそうなんじゃない?
あなたが知っている私と、他の誰かが知っている私が複写画ほど同じわけがない。
なのに、他の誰かが見ている私がふいに現れた時、あなたは私の秘密を見たように思うの?あなたが知らなかっただけなのに。
皮と肉の袋の中に詰まっているものすべてをさらけ出したら、ひとのカタチを保ってなどいられないでしょう。私が私のカタチを保っているためには、たくさんのものを袋に詰め込んで閉じておくしかない。
そしてそこに詰まっているものなんて、ほぼほぼたいしたものじゃない。実は秘密でもなんでもない。
だけど、誰かと誰かでその皮と肉の袋を破ってとろとろと溶け合わせることなどできないから、その袋はひとのカタチを保ったまま孤独に存在するしかない。
まだ孤独を哀しみと確かには自覚しない幼いユジと、引き裂かれたような孤独をやさしさでくるんで生きるミンの、出会いの短い時間が記憶に残る。
チョン・イヒョン 1972年・ソウル生まれ
メモ:
世界で一番悲しい音楽 ヴィターリの<シャコンヌ> 演奏・ハイフェッツ
「ディオゲネス変奏曲」
2021年6月25日 読書アジア文学の棚から。
ポケミスの装丁とタイトルに惹かれて。
あたり。収穫~♪
陳浩基、1975年生まれの香港人。
17編の自選短編が読める。
収録されているのはSF、サスペンス、奇想譚、ユーモア、本格推理、ショートショートなどなど、タイトルのとおりの変奏曲集。
いわゆる完全犯罪的な本格推理と言われる小説はあまり好みではないのだけど、このひとの作品は意外な結末につながる多重推理に騙される快感があって楽しめた。
プログラマーをやっていたという経歴に、なるほどとも思う。
すっきりと無駄のない展開なんだけど、ロジックのためのロジックに終わってなくて、語り口はエモーショナルで。
評判の良い警察小説「13・67」も読んでみよう。
著者・今井章信。
イマイアキノブ。バンクロ、イマイさんの絵本。
絵を描いてる人なのは知ってた。
いまは音楽の比重が大きくなってるようだけど、絵を描きたくて機材も捨てて音楽やめてた時期もあったそう。ほどほどに絵も音楽もとはならないらしい。
イマイさん曰く「音楽の方が健康的」「絵は身体に悪い」んだそう。それでも絵を描く。イマイさんのそういうアーティスティックなところがいつも気になる。
インタビューも、The Birthday 、ROSSO、チバ周りのメンバーの誰よりも読んでて面白い。表現者なんだなぁと思う。
「やまのスカブラ」、コントラストの強い重い色合いだけどダークなユーモアが感じられる絵で。イマイさんっぽい。
スカブラってなに?
語源は「仕事が好かんでブラブラしてるひと」というのが一説。
九州の炭鉱で石炭を掘らずに艶話や笑い話をしてぶらぶらしている人がいて、でもいったん鉱に降りたら丸一日穴の中にいる工夫たちになぜか愛されていたというスカブラ。
絵本の奥付に上野英信の名前があって。
あれ?知ってる。
何年か前に読んだ上野朱の「父を焼く」のその父が上野英信。炭鉱労働者のルポルタージュを書き続けた人。スカブラの存在を記録した人。
まあ、こういう偶然がね。ふっと嬉しいというか。
イマイさんの表現に私が惹かれるのがうっすらとわかるような、思い込みが深まる。
岩波新書「地の底の笑い話」上野英信著よりすかぶらの話-黒い顔の寝太郎
http://www2t.biglobe.ne.jp/~cjfc/hanasi.htm
「あしなが蜂と暮らした夏」
2021年6月17日 読書ベランダに迷い込んだ季節外れのナミアゲハを保護したともだちがいる。楊枝の先でくるくる巻いた口吻をそっと伸ばして砂糖水を与えるまでして。
そういえば何年か前、羽化に失敗して飛べないアゲハが道の傍を歩いているのを見て、どうしようと思ったけどどうしようもないと思って、草の陰に入ったの見てそこを離れたことあった。ともだちなら、迷わず連れ帰ったかな?
伸枝さんは、アシナガバチの巣を女王蜂ごと紙袋に入れて東京のアパートに連れ帰った。巣の状態が悪くて放っておけないとはいえ。まだ働きバチの誕生前とはいえ。みっつも。京都から新幹線ひかりに乗って。アパートでは、部屋の中に巣を留めて、母バチのいない巣の幼虫に給餌して。
凄すぎるでしょう。アシナガバチ、ベランダの軒下にいて部屋から眺めてるのは好きだけど。給餌とか、無理むりむり(笑)
伸枝さんが描いた絵手紙風の挿画や「あしなが蜂と暮らした夏」というタイトルからほんわりとしたエッセイかなと思ったら、想像以上にしっかりとアシナガバチと「暮らして」ました(笑)
1930年生まれ。15歳で敗戦を迎えた元軍国少女らしい言葉遣いとか、なにか懐かしい匂いのする本で。子どもの頃に購読していた「学習と科学」だったかな、その中の一編を読んだような感じ。
私が眺めていたアシナガバチの生態が描かれていて、あ、そういうことだったのかぁと発見して楽しかった。
だけど、「虫好き」といっても好きの度合いはいろいろだなぁ。
私の場合は、眺めるだけでいい。私の生活圏に来てくれるのは歓迎する(いや、許す程度か?)けど、彼らの生命にまではコミットできない。だって、死んだ虫がめちゃめちゃ苦手なんだから。
赤毛のロッピは最愛の母さんの遺したバラの切り枝を持って旅に出る。
苔が生えるだけの溶岩原の北の国から、オオカミやクマのいる深い森を抜けた先の世界一のバラ園を持つ修道院を目指して。
父さんは息子が心配で、旅立ちの別れ際に「向こうに着いたら開けなさい」といって渡すのは「寝るときに父さんを思い出せるように」と、パジャマだ。初めて乗る飛行機で腹痛を起こし、着陸した先で盲腸の手術を受ける。ロッピは無事に修道院へたどり着けるのか……頼りない少年の初めての冒険…いやいや、少年ちゃうし!
ロッピには7ヵ月になる子供がいる。「あの娘、あの娘って父さんは言うけど、僕と彼女は付き合ってるとかそういう関係じゃないんだから。まあ、子どもはできちゃったけど。あれはアクシデントだったんだ」 をい?w
22歳のロッピ(あるときはダッピ、あるいはアッピ、父さんはいろんな呼び方をする)の頭の中を占めているのは、死と身体(セックス)と植物だけ。
「花の子ども」というタイトルと表紙だけで借りてきた。
メルヘン風味、ファンタジー風味かなぁと思いながら読み始めて、主人公の頼りなさにちょっと面倒くさいかなぁ~とちらちら思いながらロッピの旅に付き合う。
修道院のブラザー・トマスや彼の娘フロウラ・ソウル、そしてその母親(ロッピの妻でも恋人でもない大学生)アンナが彼の生活に登場しても、どんな物語を読んでるのかよくわからない。でもその頃には、の~んびりと遠い親戚の男の子の消息を眺めるような気分で楽しむ。
映画好きのブラザー・トマスが良い。
「一緒にノスタルジアでもどうかね」
「え、どういう意味ですか?」
「『ノスタルジア』という映画だよ。苦しんでいる人びとへの思いやりを持つには、瞳の奥ににじんだ苦しみに気づかなければならない」
遺伝学の論文を書き上げなくてはいけない24歳のアンナ。
「母親になる前にやるべきことがたくさんあると思う」
「あなたのことが信じられないほど好き。だけど私、ひとりになりたいの――あと何年か――自分を見つけて博士号を取るまで。今すぐ家庭を築くには、まだ若すぎると思う」
22歳のロッピのもとに、北の国の代表的なモチーフとなる「八弁のバラ」の枝とマリアに抱かれた幼子によく似た娘フロウラが残される。
・・・・・
2020年のジェンダーギャップ指数で153ヶ国中、121位の日本に住む私には、これはやっぱりファンタジーだったのだ。
読み終えて、解説を読むまで気づかない事ばかりだった。ロッピにイライラし、アンナに「え?」と思ったりする、その時点でジェンダーギャップ121位の国のひとなんだよなぁ。
11年連続ジェンダーギャップ指数1位で、ジェンダーロールに多様性があり、かつそれが当たり前に社会制度で保障される国では、この物語はファンタジーではなく当たり前の若い男女と家族のリアルなのだった。
原題に使われている「Afleggjarinn」という語にはふたつの意味がある。ひとつか「挿し穂」で、もうひとつは「特定の場所に続く脇道」である。日本にも挿されたアイスランドからの挿し穂が良く育ち、やがてその枝の先がどこかに繋がる道となることを、心より願っている。
朱位昌併<解説>
日本で根付くだろうかねぇ。
1975年 職場での男女格差や性別による役割分担の不平等に女性が声を上げ「女性の休日」と呼ぶストライキを決行
1980年 世界初の民選の女性国家元首が大統領に就任
2009年 同性婚をした女性首相が就任 大臣の半数が女性となる
以降、女性、子ども、ハンディキャッパーを支援しジェンダーギャップを小さくするための施策が実行される
アイスランドはちゃんとやるべきことやってきたんだよね。
挿し穂を根付かせるには、土が大事なんだね。
2002年韓日ワールドカップで沸きかえった夏、‘美貌の女子高生殺人事件’と呼ばれた悲劇が起こる、その後の事件を取り巻く人物の人生を描く。19才だったヘオンが公園で死体で発見され、犯人が捕えられないまま17年の歳月が流れる―。
<東亜書店HP>
絶対的な美貌のへリム。
容疑者とされたハン・マヌ。その妹ソヌ。
ヘリムを車に乗せていたジョンジュン。
二番目に美しい少女テリム。
転校してきた同級生サンヒ。
へリムの妹ダオン。姉妹の母。
語り手はこの中の三人。
少女が殺された、それだけでもうミステリだけれど、犯人が誰か動機は、、そんなことはどうでもいいこと。
事件が起きて、何人かがいなくなって、日常が戻ってきて。それでも事件で穿たれた空白は、ひき攣れた傷痕のようにそこにあってひとを不安にさせる。
そうよ、あの子たちは事件に遭ったり留学したり転校したり、何らかの理由でいなくなっただけ。じゃあ、残された私たちは?死にそう。何にも変わってなんかない。こうやってずっと生きていくの?これが生きるってこと?事件にはそうして終止符が打たれた。
・・・・・
理由もなく過酷な生を強いられても、私たちはその中でか弱い虫のように、過酷なことにすら気づかず生きていく。
作者の後書き。
「人は平凡に生まれ、平和に生き、平穏には死ねない」
生きることは平らかではないと知ってしまうことのイラダチ、ヤリキレナサの物語、かな。
クォン・ヨソン 1965年生まれ ソウル
最近、アジア文学の棚の前をうろうろしている。
パク・ソルメの短編集「もう死んでいる十二人の女たちと」が読み切れなくて(返却期限が来てしまって)感想書かずにいたけど。
棚を眺めていたら、韓国の現代文学がとても充実していることに気が付いた。
そして、韓国の文学についてなにひとつ知らないってことにも気が付いた。
手にとって、カバーに紹介文があればそれを読んで、なければ冒頭の3行を読んで借りてみている。このあとも何冊か読んでみたい本がある。
一番近い隣の国の物語なのになぜいままで読もうとしなかったのかな。
四度の手術で私が得たこと、それは人間は所詮肉の塊である、という感覚だろうか。<中略>
私のように意志ばかり肥大させて生きてきたような人間には、それはちょうどよい体験だったのかもしれない。独立した存在であるように思っていた精神も、所詮脳という身体機能の一部であって、身体の物理的な影響を逃れることはできない。私はそれをあまりにも無視して生きてきたんじゃなかろうか。
<中略>身体(と生活)を極限まで無視した分、得がたくおもしろいことを見れたし、学べたという自負はある。でも癌を作るまで(?)身体を本気で怒らせることになったのはまずかった。癌を通じて、私の意志は一度身体に降参し、身体のいいなりになるしかなかったのだ。
内澤旬子の本は、「世界屠畜紀行」「飼い喰い 三匹の豚とわたし」「おやじがき―絶滅危惧種中年男性図鑑」と読んでいる。先にあげた2冊は特に面白く読んだ。読んだもののタイトル並べると彼女の本は「肉の塊」がテーマなのかと思ってしまう。この「身体のいいなり」も同じく。
彼女は「幼稚園児のころから、じりつしんけい、とか、きょじゃくたいしつ、という言葉を知っていた」くらい原因不明の身体の不調に悩まされながら、意志の力で身体を引きずって日本中、世界中を旅してまわっていた。
乳癌になって意志が身体に降参し、そうすることで生まれ直したみたいに身体感覚が整ってゆくのだ。この本は闘病記ではない。自分の身体が蛹化して、一度ドロドロに溶解されて羽化して新しい肉体感覚を得るまでを取材、観察し続けてる?そんな感じ。降参しつつも手放さない意志の力で。
ちなみにこの本は4冊目の著書なんだけれど、この病気のあと回復して、千葉に引っ越して三匹の豚を飼って、その後、ストーカーと闘い、東京で老いるのは嫌だと小豆島に引っ越し山羊を飼い、狩猟免許をとりジビエ販売をやり……という暮らしをしている。
Twitterなどで山羊と格闘―文字通り身体張って―してるの見てるとタフだなぁ、武闘派?肉体派?と脱帽する。
私も年齢的なものだと思うけれど、若い頃よりずっと身体の声が聴こえるようになってきたし、その声に従っていれば案外間違いないという実感は持つけれど、こういうおもしろい著作を何冊も作り上げる人のメーターの振り切り具合はすごいなぁと思う。彼女の「意志」は実はまったく降参してないんだなぁ、と思うもん。あっぱれ。
つぎはなにを読もうかな、「漂うままに島に着き」かな?「ストーカーとの七〇〇日戦争」はもちょっと後でもいいかな(笑)